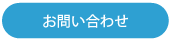会社を成長させていくためには、「売上最大化と経費最小化」を同時に進めていかなければなりません。経費削減はそのためには欠かせない重要な取組みになります。
会社経営は売上以下のコストで運営することによって初めて成立するので、経費削減、あるいは、経費コントロールは、最重要課題といっても過言ではありません。 すべての経費が無駄なく売上につながっていれば問題はありませんが、実際にはそのような会社はなく、全ての会社に無駄な経費は存在します。だからといってやみくもに経費削減を行っても期待する効果は上がらないどころか、誤った経費削減がきっかけで業績が悪化することさえあります。 今回は、中小企業における経費削減の取り組みを紹介していきます。
1、中小企業経営こそコスト削減に取り組むべき?
中小企業の売上高経費率は平均96.7%。最大97.9%(卸売業)、最小でも91.5%(不動産/物品賃貸業)とコストが占める比率は極めて大きいことが分かります(中小企業庁「中小企業実態基本調査/平成30年確報」の経常利益率より算定)。だからこそ僅かなコスト削減であっても、中小企業にとっては大きな効果があるといえます。
大企業ではコスト削減に取り組む際、部署をまたいで社内に働きかけ、体制を整えることが必要です。そのため、部署間の調整に手間がかかったり、膨大な人数をまとめてコスト削減を推進していく必要があるため「取り組みがなかなか進まない」といったことが少なくありません。
一方で、中小企業は社員数・部署数ともに限定的で、大企業と比べてスピーディに取り組みを推進することができます。そのため、コスト削減を推し進める意思決定者を明確にすれば、全社的な取り組みとしてコスト削減を実現しやすいと言えるでしょう。

2、コスト削減へのアプローチ
帳簿を見ると、多くの場合一面に支出費目がずらっと並んでいます。これではどれが問題なのか、費目をひとつ丸ごと削減すればよいのか、見当がつきませんね。
ここでやみくもにコスト削減を行うのは賢明ではありません。通常、コスト削減というと事務所経費等の固定費に目を向けがちです。固定費の代表的なものは事務所人件費ですが、これを安易に削減してはいけません。なぜなら従業員の士気低下に繋がるからです。
それでは、どこからコスト削減を進めていくべきなのでしょうか。 勘定科目には多くの費目があります。各費目には、従業員の雇用、材料や商品の購入、設備の導入など、事業活動に伴う多様なコストが日々積み重なっていきます。
日常の業務を振り返ると、以下のような場面はありませんか?
- いつもの顧客からの発注だからといって、いつも通り作る。
- まだ時期じゃないのにもかかわらず取りあえず仕入れておく。
- 無くなると困る資料だからといってコピーをとる。
- 目的が曖昧なまま会議をやる。
- この設備のほうが便利そうだからという理由で購入する。
職場で他人の行動などを見て、「ああ、もったいない」「要らないのでは?」とふと気づくことがあるはずです。コスト削減にはそのような「気づき」こそが重要なのです。

3、コスト削減の4ステップ
ここからは中小企業がコスト削減に取り組んでいくための4つのステップについて説明していきます。
ステップ1「分類集計」
分類集計とは、会社の経費がどのように使われているのかを把握することです。無駄なコストを発掘するには、どのような経費が、どの程度使われているのかを科目ごとに分解し、集計することが不可欠です。経費の分類集計は必ず年計で行います。なぜなら、経費には年に1回程度しか発生しない一過性のものが必ず混入しているからです。年間売上に対応する年間経費が集計されると、その会社の売上と経費の関係性が明確になり、コスト削減のプランが立てやすくなります。
ステップ2「適正判定」
適正判定とは、現状の経費水準がどの程度なのかを把握・判定することです。経費水準が適正であるにも関わらず、やみくもに経費削減を進めた結果、様々な衰退リスク(売上減少・生産性悪化・品質低下等)を招いては元も子もありません。
経費の適正水準は売上総利益高経費率で判定します。
売上総利益高経費率=(総経費÷売上総利益)×100
売上総利益高経費率が90%以下であれば比較的緩やかな経費削減方針で大丈夫だが、売上総利益高経費率が90%以上の場合は、なるべく速やかに経費削減を進めるべきです。
売上総利益高経費率が100%を超えている場合は、赤字経営(売上よりも経費が多い)に陥っているという事なので、すぐさまコスト削減を進める必要があります。
ステップ3「対象選定」
中小企業の経費削減では、なるべく年計金額の大きい部分を対象に選定するのが効果的です。上位コストの水準を、競合他社よりも抑える事ができれば、競争優位性が飛躍的に高まるからです。経費削減の方法論として効率改善もお薦めで、例えば、自動消灯、自動ドア、IT活用などの自動化推進、最新の技術やノウハウを取り込んだ業務効率化等は経費削減に有効です。また、節約や文具の共有化も経費削減効果があります。 ひとつだけ気をつけなければならないのが、商品やサービスの品質を下げる経費削減や社員の安全を損なうコスト削減だけは絶対にやってはいけないということです。
ステップ4「リスク検証」
コスト削減を実行した場合に、会社経営に及ぼすマイナスリスクを検証することを「リスク検証」といいます。マイナスリスクには、売上減少、生産性低下、人件費増加、効率悪化、品質低下、サービス低下、安全性低下、労災や事故の増加などがあります。 このマイナスリスクの検証はコスト削減において最重要作業になります。この作業を疎かにすると、コスト削減が仇となって会社経営が悪化することがあるからです。 リスク検証の方法は簡単で、例えば、マイナスリスクが高い場合は、「コスト削減を見送る」、あるいは、「コスト削減の対象選定を再検討」する。マイナスリスクが低ければ「コスト削減を実行」に移す。コスト削減後にマイナスリスクが表面化した場合は「元に戻す」といった要領でリスク検証を継続することが、コスト削減で失敗しないコツです。
まとめ
コスト削減を成功させるには、そのための“意識”を経営層と管理部門だけでなく、従業員も含めた全社で共有することが大切です。そして継続的に取り組みを続けていくことも重要です。半年、1年後の目標(金額や最終的な姿)を記した計画を作り、達成率を可視化しながら計画を進めていきましょう。

弊社では、業務効率化・コスト削減を目指すお客様のサポートを行っております。ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。