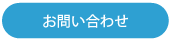生産性向上の目的は、少ないコストで大きな利益を獲得する経営基盤の確立にあります。
そのためコスト削減は生産性向上には欠かせない活動です。また、会社経営はライバルよりも低コストで商品やサービスを提供することで企業の永続性が保たれるので、コスト削減に終わりはないといってもいいでしょう。
そこで今回はコスト削減にまつわる「省くべきムダ」と「省いてはいけないもの」についてご説明します。
生産性向上とは
生産性向上」とは、保有する資源を最大限に有効活用し、小さな投資で大きな成果を生み出すことを意味します。企業にとって生産性とは、「投入した経営資源(インプット)によって、どの程度の成果・価値(アウトプット)を生み出せたか」であり、次のような計算式で表現できます。
「生産性」=アウトプット(成果)÷インプット(コスト)

アウトプットは生産量・生産額や付加価値、インプットは従業員の数や労働時間などに置き換えればわかりやすいです。100人の従業員が15,000個の製品を作り出しているなら、生産性は15,000÷100で150です。もしも75人で同様の成果をあげられれば、生産性は15,000÷75で200へと向上します。あるいは100人の従業員が20,000個の製品を作り出すことができれば、生産性は20,000÷100で、やはり200ということになります。
このように、インプット(コスト)に対するアウトプット(成果)を大きくすることを「生産性向上」と呼びます。
業務を効率化しようとすると、「ムダを省くこと」のみを考えがちですが、「成果をあげる」「仕事の質をあげる」という意識がないと、生産性向上につながらず、手抜き作業による品質低下やミスの温床になってしまいがちです。
省くべきムダ
①過剰品質のムダ
仕事をする際、「たくさん作る」「細部までこだわる」「時間をかける」などに重点を置いた品質管理は、一見良いことのようにも見えます。しかし、限られた時間の中で最大の成果を出すうえでは「過剰品質」と捉えられ、生産性向上を阻む原因にもなります。
これらのような「過剰品質のムダ」が自分の業務に隠れていないか見直したうえで、仕事の質を高めるQCDRS(品質(Quality)、コスト(Cost)、納期 (Delivery)、リスク(Risk)、セールス(Sales))の5つの観点から適正であるかを考え、改善を図ることが重要です。
②待ちのムダ
指示や決済を仰ぎたい上司が席を外していて、待ち時間が生じることはよくあります。
この待ち時間を「手持ちぶさたで何もしない時間」にしてしまうことこそが「待ちのムダ」です。
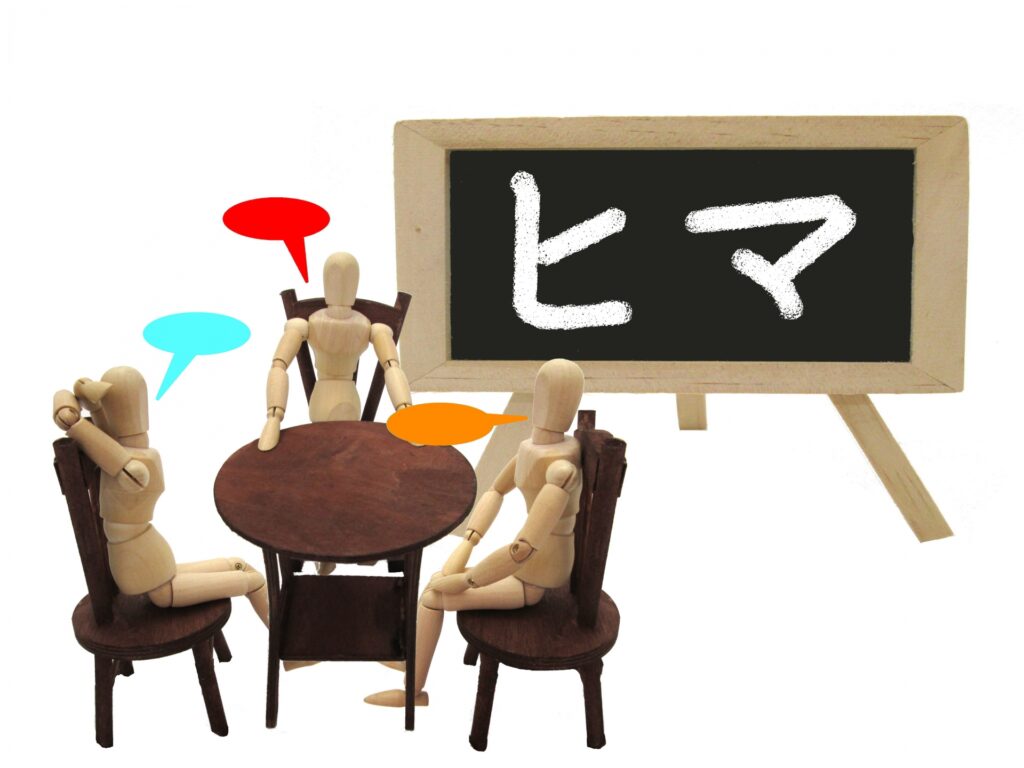
次に行う業務の手順を考えたり、新企画のアイデア出しをするなど、やれることはたくさんあるはずです。短い時間に集中して考えることで良いアイデアが生まれるケースもあるので、スキマ時間の使い方は意外と重要です。
それよりも、そもそも一日の間にスキマ時間があまりに多すぎることが問題です。
仕事の全体量を把握したうえで、同じような仕事はなるべくまとめて行い、報告の回数を減らすなど、一日のスケジューリングを改善する余地は十分にあります。
③コミュニケーションのムダ
過剰な情報は混乱を招きます。逆に、過少な情報は不要なやり取りを増やします。
バランスの取れていないやり取りは、結果としてコミュニケーションコストを増大させ、ムダを生みます。
例えば、会議がよく長引いてしまったり、メールのやりとりが多く返信だけで一日が過ぎてしまったり、といった職場では「コミュニケーションのムダ」が蔓延している可能性があります。
その場合、改善策としては、「会議ではゴールを明確にし、進行を分単位で区切るルールを作る」や「メールを見る時間を決めたり、メール以外の連絡手段を検討する」といったことが考えられます。
不要不急のやりとりを避け、適切なコミュニケーションの時間を決めて行動することができれば、ムダを削減しつつ、職場で必要な情報を共有することが可能です。
「このままでいいのかな?」と一度でも職場で疑問に思ったら、「ムダを減らせるのでは?」と立ち止まって考えてみましょう。
④分業のムダ
分業は「単純」「大量」の作業を役割分担によって効率化するためには有効です。しかし、分業が進むと他の場所や担当者ごとに何をやっているかが見えなくなり、必要なコミュニケーションも取りにくくなります。
その結果、例えば営業1課と2課が同じ顧客に同時にテレアポしてしまう、商品を発送する部署との連携が悪く顧客への提供が遅れてしまう、といった事態に陥るのは「分業によるムダ」と言えます。
改善策として、電話業務を一括して担うコールセンターを作る、反復作業の多いPC処理はRPAを導入する、といった業務の集約化や自動化を検討することも、組織全体のムダをなくすことにつながります。
⑤工程のムダ
工程が複雑であったり、必要以上に多いと、関わる人が増え、ムダなやり取りが発生したり、ミスが起こりやすくなります。何かの申請を許可する際に必要となる承認者の数がやたら多い、役割分担のプロセスが細く一つの業務で何度も往復する、といった非効率的な業務フローになっている組織は、今すぐ見直しを図るべきです。
「工程のムダ」を見つけるには、「可視化」することが何より有効です。
具体的には、業務の進め方を順序立てて整理したり、手順をフロー図に落とし込んだりして作業の流れを把握することで、客観的に問題の箇所を発見できるようになります。
また、誰と何をすればよいかもすぐに分かるようになります。
省いてはいけないもの
スピードアップを試みていつものプロセスを省いたら、ミスが発生して結局仕事が終わるまでの時間は変わらなかった、という経験はありませんか?
仕事を早く終わらせようとするあまり、チェックが疎かになってミスを連発した、その仕事をする意味を深く考えずこなすだけでクオリティが一向に上がらない、といった現状を放置していては本末転倒です。
そこで、以下の3つを大切にすることで、仕事の質を確保したうえで業務効率化ができ、真の意味での「生産性向上」が実現できます。
①考える時間
効率を上げるには「慣れたやり方の方が早く終わる」と考えがちですが、現状の仕事のやり方のままで放置してしまうと、いつまでも根本的な改善がされません。今までのやり方を「疑い」、もっとよい方法はないか、多面的な視野に立って考えてみる時間は、省いてはいけません。仕事の早い人ほど、どうすれば仕事を早く終わらせることができるか常に考え、工夫をしているものです。
また、提案書作成や企画立案など、よく考えなければできない仕事があります。
集中する時間が必要な「考える仕事」と、手を動かせば終わっていくような「こなす仕事」をよく吟味して、時間をかけるべき仕事に効率よく時間を使えるよう心がけましょう。

②コミュニケーション
「過度のコミュニケーションはムダ」と上述しましたが、もちろん適切なコミュニケーションは生産性の向上に欠かせません。
仕事を早く終わらせようとして「手抜き」なチェックをすると、ミスや不正が発生します。業務フローの中にチェック機能を組み込む、リスクの顕在化を極力防ぐために定期的にチェック担当者を変えて確認するなど、チェック体制を見直すことで仕事が上手く進みます。チェックリストやマニュアルも定期的に更新するとよいでしょう。
③チェック体制
仕事を早く終わらせようとして「手抜き」なチェックをすると、ミスや不正が発生します。業務フローの中にチェック機能を組み込む、リスクの顕在化を極力防ぐために定期的にチェック担当者を変えて確認するなど、チェック体制を見直すことで仕事が上手く進みます。チェックリストやマニュアルも定期的に更新するとよいでしょう。
まとめ
業務の中に潜む“ムダ”を省くことは、どんな現場においても意識しなければならない課題です。ムダを省くことで、工数、所要時間、コスト、人員、総労働時間などを抑えられれば、生産性も向上することになります。ただし、ムダの省略は、いわば「業務効率化」であり、インプットを小さくするための取り組みに過ぎません。重要ではあるものの、あくまで「生産性向上」へとつながる“施策の1つ”であると捉えることが望ましいです。ムダを省略して作業時間を減らしつつ、従業員のスキルアップを図って生産量を増やすなど、インプットとアウトプットの双方を考慮しながら「生産性向上」を目指していきましょう。

弊社では、業務効率化・コスト削減を目指すお客様のサポートを行っております。ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。