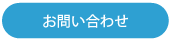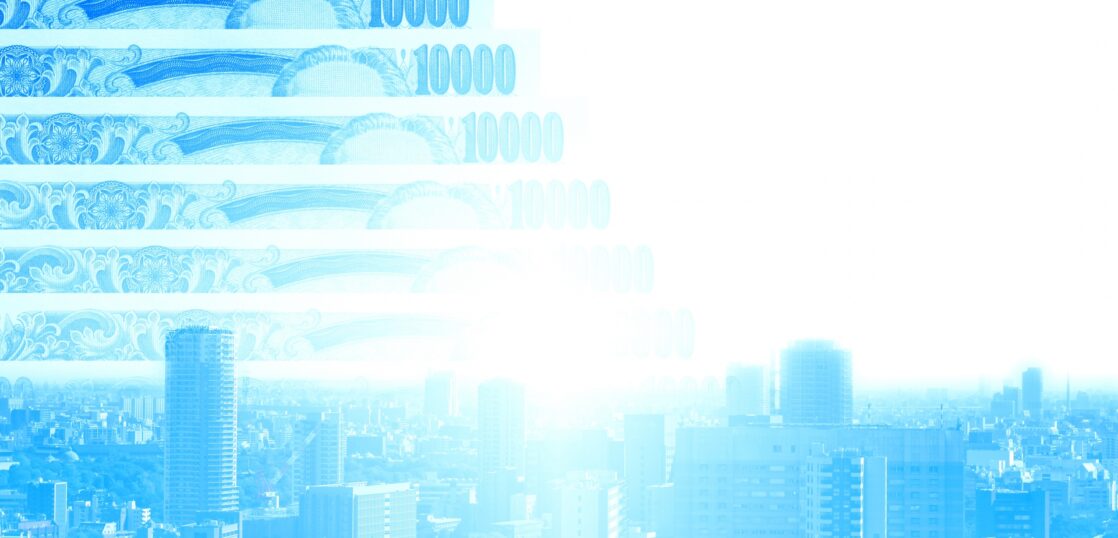市場の鈍化により、企業が低成長を余儀なくされる中でも、「コスト削減」から目を背けることはできません。中でも「調達コスト」は取り組みやすい項目です。
調達コストは直接材と副資材とに分けることが出来ます。生産に直接影響を与える原材料や部品などを直接材といいます。その価格が製造原価に大きく影響するため調達コストを引き下げることが極めて重要な資材です。また直接材は取引量や回数が多いため、各企業はさまざまな方法でコスト削減に取り組んでいます。
一方、副資材については、直接材に比べると1つあたりの取引量や回数が少ないことからコスト削減に対する取り組みはあまり進んでいません。
また、副資材のコスト削減に取り組んではいるものの十分な成果を上げられていない企業も多く存在します。直接材ほど製造原価に対するウェイトが高くないとはいえ、コスト競争力を高めるには、副資材についてもコスト削減に取り組む必要があります。
そこで今回は、副資材の調達コストを大幅に削減するためのポイントをご紹介していきます。
副資材とは
副資材とは、企業が調達する資材のうち、直接、個別の製品価格に反映されにくい資材のことです。具体的には、製造現場で使用する「工具」「ユニフォーム」「手袋」「燃料」など、またあらゆる部門で使用する「筆記用具などの文房具」「電卓・電話機などの事務機器」などのオフィス用品が該当します。
製造業において副資材は、燃料や工具などが代表的ですが、その他に事務用品など製造に関係しないものも副資材の一種です。
原材料や部品など直接製品に使われる資材は、「直接材」と呼ばれています。

副資材の調達
調達(英語:Procurement)とは、企業が自社の企業活動に必要なモノやサービスを確保する一連のプロセスのことを指します。調達はどのような企業においても必ず行われており、企業活動において必要不可欠な活動です。原材料の仕入れも、現場で使うボールペン1本を買うこともすべて調達活動に含まれます。
副資材の調達は、直接材に比べると以下のような特徴があります。
・種類が多く購入数
・金額が少ない(多品種少量発注)
・社内の全部門が発注部門(多数の発注窓口)
・購入先が多岐にわたる(多数の仕入れ先)
多くの場合、直接材は、少品種であり大量発注が可能であるため発注窓口を集約でき大幅なコスト削減が可能です。
一方で、副資材は上記のような特徴からコスト削減しにくく、多くの企業が課題を抱えています。しかし、厳しい価格競争を乗り切って利益を上げるためには、副資材のコスト削減まで徹底して行うことが必要です。売上が簡単に伸ばせない時代には、コスト削減に注力して利益を増やしていくことは極めて重要なのです。
また、副資材の調達を業務の合間に行えるとしても、会社によって一定額以上は決裁や相見積もりを取ることが必要と定められています。仕入れる副資材の品質や納期の管理など、面倒な業務が必要になることもあります。これらの業務を各部門ですべて合計すると、意外に見えないコストとして無視できないほど大きい可能性があります。これらの理由により、副資材の調達を効率化し、コスト削減を進める必要があります。
副資材調達における課題
①発注する品種・点数がとにかく多い
副資材調達の効率化がなかなか進まない1つ目の理由は、発注する品種・点数がとにかく多いことです。副資材の定義は幅広く、細かいオフィス用品も含まれることからその全体像を掴んでいる調達担当者は少ないでしょう。それが、副資材調達の効率化を阻む原因でもあります。
品種・点数が多いことで在庫管理も難しいため、棚卸資産の把握もできなくなります。そのため主資材のように手の行き届いた管理ができず、副資材調達にどれくらいのコストがかかっているかも把握しづらくなるのです。
②部門ごとに発注しているため管理が複雑
主資材の発注を取りまとめているのは調達部門・購買部門であっても、副資材の発注は部門ごとに行われているケースが少なくありません。部門ごとに使われやすい副資材は微妙に異なるので、一見して部門ごとに発注する方が効率的なように思えます。
実際のところは、部門ごとに副資材を発注してしまうと発注プロセスがバラバラになり、かつ在庫管理などが徹底されていないことから無駄なコストがかかっているケースが大半です。また、調達担当者が後から副資材を管理しようにも、部門ごとに分散してしまっているため全体管理が複雑になります。

③仕入先が多数存在しコスト均一化が図れていない
副資材調達が部門ごとに分散すると、部門ごとに異なる仕入先が存在することになります。そうすると、異なる部門で同じ副資材を仕入れたにもかかわらず、一方の部門の方が仕入れコストが高くなり、コストの均一化が図れません。
副資材調達の基本は「同品質のものをできる限り安く仕入れる」ことです。部門ごとの仕入はこの基本が押さえられなくなってしまうため、副資材にかかるコストが膨らみ、馬鹿にできない金額に達します。
④基本となる調達計画が無い
主資材には生産計画から落とし込まれた調達計画・購買計画が常に存在します。一方、副資材にはそれがありません。生産に直接かかわりが無いため、「何を、どれくらい、いつまでに」必要なのかが把握できず、「必要になった時に発注する」スタイルが確立します。
これでは当然調達の効率性が下がってしまいますし、徹底した管理ができないため無駄なコストが発生する可能性もあります。
これまで、副資材の合理化は難しく、その効果は大きくないと考えられてきました。徹底管理は主資材ばかりに集中し、副資材調達の管理に注力するような企業は少なかったでしょう。しかし現在になり、色々とIT環境が整ってきたことで副資材調達の効率化も現実的な話になっています。また、厳しい価格競争を乗り切るためには副資材の削減にまで手を伸ばし、徹底した原価低減活動が必要となります。
副資材調達の効率化のためには
製品価格を下げなくても、副資材調達の効率化によって原価が少しでも下がれば、それは企業利益に反映されます。では、副資材調達を効率化するためのポイントはどこにあるのでしょうか?
①発注窓口を一元化して、プロセスとコストを均一化する
まずは当然ながら、部門ごとに分散していた発注窓口を調達部門・購買部門に一元化しましょう。発注窓口が分散していると効率的なプロセスを組むことが難しいですし、コストの均一化も図れなくなります。副資材発注の際は、各部門が調達担当者に発注依頼を行い、担当者が定期的に発注をかけます。一見非効率なように思えますが、プロセスとコストの均一化を考えるとこちらの方がはるかに効率的な調達です。
②調達担当者同士で情報共有を怠らず低コスト化を図る
主資材に関する情報は調達部門・購買部門内で標準化されていることが多いですが、副資材に関する情報が共有されていないケースが多いです。副資材の低コスト化を図るためには、調達担当者全員が同じ情報を共有して、高品質・低価格な副資材を調達しなければいけません。そのために情報共有を怠らないでいると、低コスト化だけでなく調達ノウハウの共有にも繋がり、調達効率を大幅にアップできます。

③副資材の調達方法をマニュアル化して誰でも調達できるようにする
副資材の調達を行える担当者が限定されてしまうと、属人化によって調達効率が下がる恐れがあります。どんな作業にも言えることですが、積極的にマニュアル化を図って誰でもその作業ができるようにすることで、効率性はアップしますし、業務リスクも回避できます。副資材の調達方法に関してもマニュアル化を行い、誰もが同じように調達できるようにしましょう。
まとめ
間接材は、企業のコストダウンを推進するときに意外に見落とされている場合が多いです。一見、それほどコストが膨大化していないように見えるケースや、これ以上下げられないように見えるケースでも、間接材に対する視点を変えることで最適化できる可能性があります。また、1回の調達では小さな支出・作業量でも、積み重なれば大きなコストになります。言い換えれば、副資材の扱いを見直すことで、大幅なコストダウンが見込めます。副資材に関する無駄を見直して、利益の最大化を推進していきましょう。

弊社では、業務効率化・コスト削減を目指すお客様のサポートを行っております。ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。